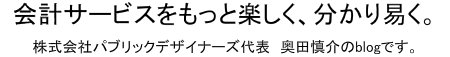2008年4月1日火曜日
2008年3月27日木曜日
決算を粉飾する②
そこで
1)取締役がお互いに監督を行う取締役会により、
2)経営の監督を行う目付け役である監査役により、
3)監査の専門家である会計監査人により、
経営者の監督を行うような仕組みがルールとして決められています(経営の内部牽制)。
もし、経営者が不適切な予測や選択により粉飾を行おうとする場合、監査役や会計監査人は不適切であることを利害関係者に報告します。それにより、間接的に粉飾を抑制しようとしているわけです。
【経営環境の重要性】
上記のような経営者の誠実性や経営の内部牽制を全てひっくるめて経営環境といいます。そしてこの経営環境が適正であれば、粉飾は事前に防止されるはずです。逆に考えると、粉飾の可能性は、経営環境が適正かどうかで判断できることもあるということです。例えば、
・頻繁に会計方針を変更する
・収益予想を頻繁に下方修正する
・ディスクロージャーが度々遅延する
ような場合は経営者の誠実性という経営環境が怪しいと疑うべきでしょうし、
・監査役や社外取締役に多額のストックオプションが付与されている
・一身上の都合で役員が短期間に頻繁に辞任している
・会計監査を担当する監査法人が期中に突然辞任している
・監査報告書に問題事項が指摘されている。
ような場合は、経営の内部牽制という経営環境が働いていない可能性があります。
決算書を分析する上で、経営環境の理解はとても重要です。
2008年3月24日月曜日
決算を粉飾する①
【したいという動機としなければならないという動機】
多くの企業は決算における利益をもとに役員報酬やボーナスを決定します。とすれば、決算報告は株主に対して経営者の成果をアピールする大きな機会です。さらに、決算がよければ株価は大きく上昇するかもしれません。すると、ストックオプションを保有する役員にも大きな利益をもたらすことになります。
もし、多額の報酬、ボーナスやストックオプションの利益を得ることのできる可能性があるのならば、粉飾をしてでも業績を良く見せようという動機は起こりえますよね。
一方、銀行や取引先、あるいは国やお役所に対して一定の業績結果を示さなければならない会社もあります。銀行からの借入金について一定の自己資本比率を下回った場合に一括返済する条件(いわゆる財務制限条項)や、ある一定水準の利益を計上しないと業務免許が取り消されてしまうような行政規制を付けられている会社です。
もし、これらの条件をクリアしないと会社が潰れてしまう状況だとしましょう。そうならば、粉飾をしてでもそれを業績をよく見せようようとする動機も十分に考えられます。
【予測と選択というルール】
普通、儲かったかどうかを皆さんはどう判断されるでしょう?お金が増えたか減ったかどうかの事実で判断すると思います。
ところが、会社の決算では違うのです。実際にお金が増えたり減ったりする前に、増える減るという(原因に基づいて)予測を経営者が立てて、儲かったかどうかを判断してしまいます。
つまり、お金の動きと関係なく、むしろそれより先に儲けを決めてしまうのです。これを発生主義といいます。
もちろん、予測は経営者の好き勝手にできるわけではなく、ある一定の条件に縛られるわけですが、この一定条件も複数あり、選択することが可能です。
例えば、商品を売るときには、
1)商品を出荷したときに儲かったと判断する方針
↓
商品出荷時点で売上をたてる。
2)商品が相手に研修されたときに儲かったと判断する方針
↓
商品検収時点で売上をたてる。
といった条件が選択できるわけです。
このような選択できる条件を会計方針といいます。
するとどうでしょうか。粉飾をしたい経営者は、当然、儲かっているという予測を立て、自分の予測を裏付けることができる会計方針を適用したいと思うはずです。
もちろん、動機があっても、それを実現できる余地がなければ粉飾はできません。ところが、企業会計は予測と選択というルールを導入しました。その結果、粉飾の動機がより実現されやすくなる余地が作り出されてしまったともいえなくはありません。
2008年3月21日金曜日
少額交際費Q&A
【少額交際費とは】
1人あたりの負担額が5,000円以内のビジネス上の接待交際経費。全額経費にできます。定義については、タックスアンサー 法人税 No5265 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm が参考になります。
Q1:社内で従業員の結婚祝いパーティ等を行ったのですが、この場合の費用も少額交際費となりますか?
A1:福利厚生費とできる可能性はありますが、少額交際費とはできないと思います。なぜなら、少額交際費とするためには社外への接待という事実が必要であり、社内交際費は交際費ですが、少額交際費には該当しないからです。 従業員に一律に適用される福利厚生に関する規定が存在し、当該規定に基づいたものであれば、福利厚生費になると思います。
Q2:お客さんが来社し、社内で出前を取りました。この場合も少額交際費になりますか?
A2:金額的条件を満たしていれば、出前も少額交際費になると思います。取引先への接待交際の目的と事実があるので、場所が社内でも、大丈夫だと思います。ただし、お土産品のようなものについては、少額交際費の範囲からは外れるので注意してください。
Q3:お店からお土産を包んでもらった場合は、それも少額交際費とできますか?
A3:飲食費とは別でお土産を包んでもらったような場合は、少額交際費にはならないと思います。なお、飲食した場合に当然セットになっているようなお土産は、そのお土産代も含めて少額交際費に該当するか判断をします。
Q4:親会社や兄弟会社の役員に対する接待交際費は少額交際費とできますか。
A4:別法人であれば、親子兄弟関係は関係ありません。税法上は、法人格が別であれば社外と考えます。親会社、子会社、兄弟会社であっても全く問題ないです。
Q5:参加者を明確しないと少額交際費とできないそうですが、具体的にどのようにすればよいのですか?
A5:お客さんを○○社○○部○○氏と特定できるようにしてあれば十分です。あわせて社内の参加者同じような形で特定できるようにしてあれば万全です。具体的には領収書に直接記載してもよいですし、『少額交際費申請書』とかを作成し記載してもそれはそれで構いません。
Q6:少額交際費と会議費との区分がよく分かりません。
A6:少額交際費はお客さんとかの接待に要した経費で、会議費は社内や社外での業務会議に要した経費です。つまり、その目的が接待交際か会議かという点で明確に違います。よって、少額交際費とするには接待の事実を、会議費とするためには会議の事実を証明する必要があります。議題や参加者を領収書にメモ書きしておけば、会議事実を一応は証明できますが、やはり業務のために会議をするのですから『会議費申請書』を作成保管しておくのがベストです。 なお、お酒が入った会議などはビジネス上ありえませんから、アルコールが入っている場合は会議費としてはまず認められないです。
以上、参考にしてください。
2008年3月18日火曜日
税務戦略を福利厚生とする
もちろん、合法の範囲内では問題のあるものではありませんが、自分たちの利益追求のみをしている、なんか後ろめたい、悪いものみたいな感覚がある。節税から連想されるがイメージが、なんとなく良くないのはそのようなところに原因があるのかもしれません。
しかし税金対策を、経営者や会社だけでなく、従業員も含めたメリットの追求、さらにはそれを最終的に株主や社会に対して還元するために行うものと考えたらどうでしょうか。すると、何のために税金を減らすのか、減らした税金をどのように活用するのか、そうすることで皆をどうやってハッピーにするのかまで考えるはずです。ここまで考えたものが税務戦略だと思います。
【福利厚生にも現れる意識の違い】
雇用対策として従業員に対する福利厚生を充実させている会社もたくさんありますが、そこにも税務戦略という意識があるかないかが現れているような気がします。
よく知られている従業員の福利厚生として社宅と食事支給があります。会社によって、いろいろなやり方があると思いますが、例えば、A社とB社がそれぞれ下記のような方法を採用していたとします。
・社宅制度
A社=住宅手当として、給料に上乗せ支給
B社=会社が社宅借上げ、住宅手当相当額を給料天引き
・食事支給
A社=残業食事代を給料に上乗せ支給
B社=会社が食堂を用意して、現物支給、給料から天引き
一見、両者に違いはないように思えるかもしれません、しかしながら、従業員の立場から考えると、実質所得には大きな差が生じてきます。
給与月額50万円、住宅手当10万円の従業員の場合、単純計算ですが、A社で働くのとB社で働くのでは、月額手取り2.7万円位も差(B社の方が多くもらえる)が生じます。もちろん、従業員の諸条件により差額は変動しますが、B社の方が手取りが多くなる事実は変わりません。
確かに、住宅手当として支給しようが、借上げにしようが、基本的にそれによる会社のコスト(支払うべきお金)は同じですし、会社として支払う税金も同じです。
しかし、従業員もハッピーになれる方法はないかまで考え、借上げや食堂を用意する手間とコストをかければ、従業員にとっては大きなメリットが生じます。税務戦略は立派な福利厚生になります。
会社がどのような意識をもって税金対策をしているのか、比較してみるのも面白いかもしれませんね。
2008年3月15日土曜日
現金以外で給与を支払う④
それは、会計基準が自己株式は資本の払い戻しと考えていることによります。
【現金支給と自己株式支給の比較】
従業員から見ると、自己株式はこれを給与として支給できることから分かるように、それ自体にプラスの価値があるものです。つまり、この点に関しては現金給与となんら異なる点はありません。
現金給与を支払った場合は、
(借方)費用 ×× / (貸方)現金 ×× →損益計算書
(借方)利益剰余金 ×× / (貸方)費用 ×× →貸借対照表
と損益計算書を経由する処理がされます。損益計算書を経由するため、最終的には利益剰余金が減少します。
であるならば、自己株式を支給した場合も
(借方)費用 ×× / (貸方)自己株式 ×× →損益計算書
(借方)利益剰余金 ×× / (貸方)費用 ×× →貸借対照表
と処理されるべきです。
しかしながら、会計基準はこれと別の考え方をしています。
自己株式は取得した時点で、(なぜか)資本が払戻されると考えているのです。したがって、自己株式を会社が取得した時点で、
(借方)資本剰余金 ×× / (貸方)自己株式 ×× →貸借対照表
と上記の仕訳を圧縮したような形で、一気に損益計算書を経由しない処理がされます。損益計算書を経由しないため、最終的には資本剰余金が減少します。
【自己株式のワンステップ処理】
つまり、会社が自己株式を取得後に給与として支給しても費用計上されないのは、既に取得時点で、損益計算書を経由せずに処理が完了してしまっているからなのです。
①自己株式の取得時点で一気に処理が行われる点、②損益計算書を経由しない処理が行われる点が、ポイントです。
取得時点で既に価値はゼロと考えている以上、その後、それをタダで従業員に支給しようとも、会計上はなんら関係しないということですね。
2008年3月12日水曜日
現金以外で給与を支払う③
【自己株式を給与とした場合】
前回と同じ条件で、時価9万円の自己株式(取得時の時価も9万円とします)を給与として支給した場合の結果考えてみます。自己株式に関する会計基準に従って考えると、
自己株式の支給時受取金額-自己株式の取得原価=自己株式処分損益
よって、
0円(給与として支給するので受取金額0円)-9万円=△9万円
となります。
この『自己株式処分損益』は損益となっておりますが損益計算書は経由しません。資本取引として『自己株式処分損』がその他の資本剰余金に計上され、貸借対照表上の処理だけで完結してしまいます。
つまり、自己株式は、従業員に支給しても費用計上がないのです。
【3つの給与支給方法を比較すると】
現金支給、ストックオプション発行、自己株式支給のそれぞれの方法による会計上の処理を簡単に比較してみます。
前回と同じく従業員に9万円(相当額)の給与を支給するとしましょう。この場合の支払方法としては下記の3つの選択肢があるのですが、
1)現金9万円を支給→9万円が費用計上
2)公正な評価額が9万円のストックオプションを発行→9万円が費用計上
3)時価9万円の自己株式を支給→資本項目から控除のため、費用計上無し
のように、いずれも経済的には同じ価値を支給しているにもかかわらず、その支払方法の違いで異なる会計処理が行われることになります。
語弊があるかもしれませんが、上記から考えると、自己株式を給与として支給することは費用計上を行わずに給与を支払える方法であると言えるかもしれません。
取得に際してキャッシュの流出はありますが、それは1)現金支給の場合も同じですし。
給料をもらうほうの希望も関係しますが、自己株式の活用も検討する価値はありますね。
2008年3月10日月曜日
現金以外で給与を支払う②
【支払時点では同じ扱いとなるはず】
例えば、1株当たりの時価が10万円の会社を考えてみます。この会社において9万円の給与を現金とストックオプションのいずれかで従業員に支払うとすると、
1)ストックオプションを発行する場合
9万円の相当のストックオプションですから、行使価格1万円で発行することになります。時価-権利行使価額=公正な評価額 ですから、10万円-1万円=9万円ということです。
条件の簡略化のため付与日=権利行使可能日とすると、9万円が費用として計上されますね(費用配分方法についても前回参照)。つまり、従業員への給与として9万円分の価値が消費された結果となります。
10万円の価値がある株式を1万円で購入できる権利を給与として渡したと考えると分かりやすいですね。
2)現金給与を支払う場合
では、9万円を現金で従業員に支払った場合はどうでしょう?もちろん、企業価値の消費は9万円です。
【支払以後においても同じ扱いとなるべき】
上記から、ストックオプションを発行した場合と、現金給与を支払った場合で、違いは生じないはずとの結論が出てきます。
ストックオプション会計基準の趣旨は"現金で給与を払った場合とストックオプションで払った場合とで同じ結果になるべき"という点にあるので、同じ結果となるのは当然といえば当然です。
であるならば、報酬を支払った時点以降においても違いが出てくるべきではないはずです。つまり、
現金給与で支払った場合は支払時点で企業価値の消費はFIX
↓
後で追加の費用計上をする必要はない
よって同じように、
ストックオプション発行の場合も支払時点で企業価値の消費は確定させるべき
↓
ならば、将来に時価が上昇しても、公正な評価額を見直して追加費用を計上するのはおかしい
ということです。
ストックオプションを発行した時点で、ストックオプションの価値増減と企業価値の増減とは分離されてしまうということですね。
このように考えると”見直し規定”がないのはやはり理論的に正しいと思い直しました(後で基準をきちんと読み込んでみたら明確に『見直さない』との記述がありました)。
2008年3月7日金曜日
現金以外で給与を支払う①
まずは、ストックオプション関するルールから考えてみます。
【会計基準によるルール】
上場企業、上場準備企業に関してはまず一番関係してくるのが企業会計基準によるルールです。
『ストックオプションを付与する時点の付与時点の公正な評価額を費用計上する。』
という基本原則です。
なんと、ストックオプションを付与すると、原則費用計上が必要なのです。お金が出ているわけではないのに…。
で、会計基準の基本趣旨を簡単に説明すると、公正な評価額とは、簡単にいってしまえば株価から権利行使価額を差し引いたものだと考えてもらって構いません(正確には違うのですが…)。なお、株価がついていない上場準備会社では、公認会計士に自社の株価を算定してもらって、そこから権利行使価額を差し引いて求めます。
例えば、株価@100円、権利行使価額@60円の場合は、@40円が公正な評価額となります。
そして、費用計上した金額はストックオプションの付与日(ストックオプションをあげた日)から実際に権利行使が可能となる日までの期間で按分します。
例えば、×1年1月1日が付与日、×2年12月31日が権利行使可能日の場合は2年間で按分することになります。上の例でいうと、毎年@20円が費用計上されるわけです。もし、付与日=権利行使可能日の場合は、付与日に全額費用計上します。
現金で報酬を支払うならば費用となるのに、ストックオプションという権利で支払うと費用にならないのおかしいですよね?
そこで、ストックオプション会計基準を適用して、ストックオプションを報酬として付与した場合の費用も計上させようしているのです。
【会計基準をよく読んでみると…】
ストックオプション会計基準は、役員、従業員に付与したものについてのみ適用対象となっています。つまり、社外の協力者に対して付与したものについては、ストックオプション会計基準が適用されず、費用計上が必要との明確な記述がないのです。この点少々不備かなと思います。いろいろと画策できそうな気がしますね。
あと、ストックオプションの評価額の見直しの規定が存在しません。アーリー時点でとりあえず、ストックオプションを付与しておけば、実際に公開できそうで株価が大きく上昇しそうな場合でも評価見直しの必要がなさそうです。アーリー段階で大幅赤字の会社なら、前記の公正な評価額もほぼゼロ、会計上認識する費用もほぼゼロなこともありそうです。ストックオプションを大量に発行(資本政策を無視したとして)する動機にもなりそうですね。
2008年3月4日火曜日
小口現金から始める内部統制
そうすると、会計監査人からは内部管理のイロハができてないと言われたり、税務署からは管理がずさんで税金を取りやすい会社と思われたりしますよね。
【現金を管理する必要性】
では、そもそも内部統制上、現金管理をきちんとしないとならない理由は何のでしょうか?
それは、『現金あるところにリスクあり』だからです。つまり、現金を持つことは、同時に横領や着服の不正が発生するリスクも持つことになるのだから、ちゃんと管理しなさいよということです。
ゆえに、ベストな現金管理方法は、『保有しない・動かさない』ということに尽きます。つまり、
「どうしたら保有する現金を必要最小限にできるのか?」 と、「どうしたら現金を動かさない仕組みができるのか?」
を満たす管理を考えなくてはならないのです。
よくよく調べてみると、不必要なほど多額な小口現金を持っていたり、仮払金が現金精算で行われていたりと、改善すべきポイントは意外とあるものです。 そこで例えば、
・日常業務から最低これだけは必要な現金を計算して、それ以外は全て預金にしてしまう
・日常業務においては全て振込を利用して現金自体での取引をなくてしまう
こんな管理方法をやっている会社もあると思います。
【現金実査の必要性】
さらに、内部統制の観点からは、持っている現金については 、『管理責任が明確になっている』 ことが必要です。 だから、会社は、(面倒くさいのですが)
毎日必ず実査をして→上司に確認してもらって→上司の承認印もらう
といった形で、誰がどういった管理をしているのか明確にしているのです。当然、不正を起こさせないためにも、実査は必ず複数名体制で行います。
経営の目的はお金を稼ぐことなのですから、稼いだお金を管理することは経営の最も基本的な事項です。 まずは現金管理から管理体制の見直しをしてみてもいいかもしれませんね。
2008年3月3日月曜日
役員報酬をいつから支払うか①
『定時株主総会で変更した役員報酬は、いつから支払って大丈夫なの?』
株主総会の翌月の役員報酬支給日から変更後の役員報酬を支払った方が安全だと思いますよと回答してます。
例えば、12月決算の会社で株主総会を2月15日に行っている会社の場合は、役員報酬の支払日毎月25日であるならば、3月25日から変更後の役員報酬を支払うということですね。
【役員報酬と会計期間の対応関係】
と考えるのには、もちろん自分なりの理由があります。というのは、役員報酬は取締役や監査役としての職務執行に対する報酬なのだから、働いた期間に対応する支払いをするべきだろうと考えるからです。
もう少し具体的に説明すると、例えば、株主総会が2月15日の会社で、役員報酬が当月末〆の当月25日払いのような場合、2月25日から変更後の報酬を支払ってしまうと、下記のような問題が生じますよね。
1)定時株主総会で前期の報告を終えた時点で、役員については実質的に、新たな職務執行責任が開始されている。 株主への報告を終えた時点でその会計期間の役員の責任が終了するからです。
↓
2)当然、新たな職務執行責任はどんなに早くみても、株主総会の翌日から開始されることになる。
↓
3)にもかかわらず、2月25日に変更後の役員報酬を支払うと、新たな職務執行責任を果たしていない期間(2月1日~2月末日)に対して、変更後の役員報酬が支払われたことになりマズイ。
そこで、上記のような場合は3月25日に変更後の役員報酬を支払うべきなのではないかと思うのです。そうすれば変更後の役員報酬は、3月1日から3月末日に対する職務執行に対する対価なので、上記のような問題が生じることはないですし。
【証拠書類の作成も必要】
もちろん、定時株主総会で、職務執行責任の開始日を3月1日から開始する旨を決定して、それを後日証明できるように議事録を作成しておくべきことは言うまでもありません。 株主の意思がそうであったことを示しておくことが肝要です。